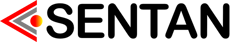2025年、AI戦略は重大な岐路に立たされている。MITの衝撃的なレポートが「生成AIを導入した企業の95%でROIがゼロ以下」という事実を突きつけたからである。この市場の失敗は、あらゆる知識を単一の巨大モデルに詰め込む「超越的モノリス」という開発アプローチそのものが持つ、根源的な構造的欠陥を示すものである。
巨大AIが期待を裏切った理由として、第一に、トップダウンで導入された高価なAIが現場のニーズと乖離し、価値を創出しているのは皮肉にも従業員が個人で使うChatGPTなどの「シャドーAI」であった点が挙げられる。第二に、AIの大家ヤン・ルカンが指摘するように、現行LLMのアーキテクチャは本質的に「幻覚(ハルシネーション)」と隣り合わせであり、業務に不可欠な信頼性を担保できない。さらに、複雑系科学のデイヴィッド・クラカワーは、LLMが世界を「理解」せずテキストを統計的に「圧縮」しているに過ぎないと警告する。この「理解なき知性」への全面的な依存は、我々自身の思考能力が衰える「認知的萎縮」という深刻なリスクを招くのである。
市場の失敗、技術的限界、そして科学的本質、これら全てが、モノリスの終焉と新たなパラダイムへの移行が必然であることを示している。その答えが、専門性を持つ多様なAIが協調する「共生的エコシステム」である。
目指すべきは、人間を「代替」する万能AIではなく、人間を「増強」する信頼性の高い専門ツール群であり、その基盤はオープンソースであるべきだ。自然界が示すように、特定の業務に特化した複数の小規模言語モデル(SLM)や、外部データベースを参照する検索拡張生成(RAG)などが連携する方が、単一のモノリスより遥かに強靭で効率的である。このエコシステムの生命線は、最高のモデル作りを目指す「モデル中心」から、最高のデータを整備する「データ中心AI(DCAI)」へと戦略の重点を移すことにある。
巨大モノリス路線は持続不可能であり、連携型エコシステムへの移行は歴史的必然である。このアーキテクチャの転換は、もはや一企業の努力で成し遂げられるものではない。エコシステムの基盤となる信頼性の高いデータインフラとオープンソースのモデル群は、道路や電力網と同様の「デジタル公共財」として、国家が戦略的に整備すべきである。
知性のアーキテクチャを選択することは、未来の社会構造を選択することに他ならない。中央集権的でブラックボックスなモノリスに知性を委ねるのか、それとも、分散的で透明性の高いエコシステムの中で人間とAIが共生し、互いを高め合う道を選ぶのか。その答えは、自明であろう。
#AI戦略 #生成AI #LLM #エコシステム #データ中心AI #国家戦略