我が国におけるIT技術史を通じて毎度のことではあるが、今回のAI技術トレンドの中でも相変わらず「国産LLM/SLM(大規模言語モデル/小規模言語モデル)」という接頭辞に「国産」を付ける風潮が観られる。その技術スタックを詳細に分析すると、我が国のデジタル赤字を構造的に悪化させかねない、深刻な共通構造が明らかとなる。
多くの「国産LLM/SLM」は、海外のオープンソースFoundation Model(例:Llama、Mistral AIのモデル群)を基盤としている。これに日本語コーパスを用いたInstruction Tuningや、特定のドメインに特化した継続事前学習(Continual Pre-training)を施すことで、派生モデルとして開発されているのが実態だ。そして、その根幹をなす学習・推論インフラは、NVIDIA製アクセラレータと主要CSP(Cloud Service Provider)が提供するコンピューティングリソースに完全に依存している。この構造は、付加価値の源泉であるはずのAI開発が、結果的に基盤技術とインフラの利用料として海外企業へ巨額の支払いをし続けることを前提としていることを意味する。
この技術構成において、日本語データセットを用いたFine-Tuningという工程をもって「国産」とラベリングすることの妥当性には、大きな技術的議論の余地があると言える。これは、ソフトウェア開発に例えるならば、著名なオープンソースリポジトリをフォークし、ローカライゼーションパッチを適用したものを「国産ソフトウェア」と呼称するのに近い感覚である。このモデルが国内で普及すればするほど、基盤モデル、GPU、クラウドという核心部分の利用料が海外へ流出し続け、我が国のデジタル赤字は益々悪化の奈落への路を辿ることになってしまう。
このようなラベリングがなされる背景には、技術的・ビジネス的要因が複雑に絡み合っている。ゼロから大規模モデルを事前学習する莫大なコストと技術的障壁を回避しつつ、「国内事業者によるサポート」や「データ主権の確保」といった非機能要件を訴求することで、市場でのポジショニングを確立しようという戦略が見て取れる。特に、公共調達における要件が、この技術的・経済的な海外依存構造を温存・加速させている側面は否定できない。
もちろん、高品質な日本語データセットの構築や、特定のタスクに最適化されたチューニング技術は、それ自体が価値ある知的財産であることは間違いない。しかし、その価値を「国産」という言葉で包括し、技術的本質とそれに伴う経済的従属構造から目を逸らすことは、長期的に見てエコシステムの分断や技術的負債の蓄積を招きかねない。グローバルな技術潮流やState-of-the-Art(SOTA)から乖離した、いわゆる「ガラパゴス」な進化経路を辿るリスクを内包していると言える。
真に問われるべきは、ラベルの有無ではなく、技術スタックのどのレイヤーで独自の価値と競争優位性を構築し、経済的な自立性を確保するかという戦略である。 オープンな技術エコシステムに貢献し、その中でいかに不可欠な存在となるか。この視点なくして、本質的なイノベーションも、デジタル赤字からの脱却も生まれないのではないか。
#LLM #SLM #FoundationModel #InstructionTuning #MLOps #GenerativeAI #AI #技術戦略 #エコシステム #オープンソース #IT業界 #デジタル赤字
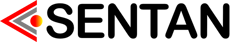
まだコメントはありません。